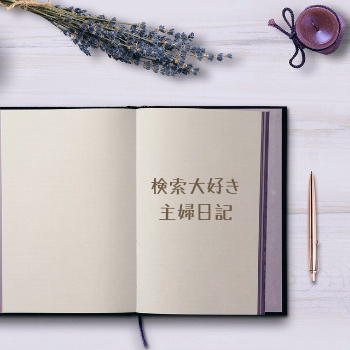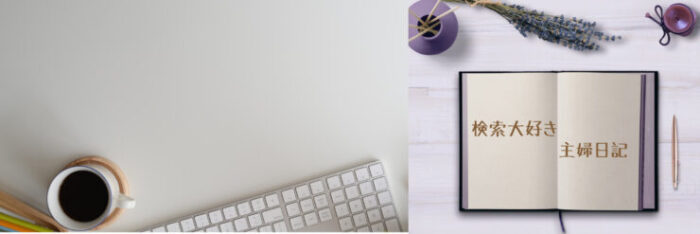子供に地頭がよくなって欲しいと願う親はたくさんいるのではないでしょうか?
私もその一人です。勉強ができる賢さではなく、人とうまく関わり、楽しく充実した人生を送ってほしい。親として私はどうサポートしてあげたら子供たちが自分に自信を持って楽しく過ごしていけるのか、そんなことを毎日のように考えています。
そんな日々の中、最近本の要約のYouTubeチャンネルでたまたま聞いていて興味が沸いた本があり、これは子供の地頭を良くするという視点で私にも出来ることがありそうだと思った本がありました。↓
この本のYouTubeチャンネルをいくつか聞き自分の子育てで生活に取り入れることが出来て、それが子供の地頭を育てられるなら取り入れてみようと思ったこと、今特に地頭がとか意識せず取り入れている事も地頭を良くすることに繋がっているのでは?ということをまとめました。
子どもの成績アップ 効果で選ぶなら 【RISU算数】参考にした動画
地頭が良いとは?
地頭は鍛えられるのか?
意識的に脳の前頭前野を鍛えることで可能
- やる気
- 集中力
- 記憶力
- 論理的思考力
- 客観的思考
- 行動や感情のコントロール
- コミュニケーション
などをつかさどる脳の最高中枢⇒人間らしい大人な活動を作る部分
前頭前野が発達している人は
- 人付き合いがうまい
- 目先の利益にとらわれず、長期的に見て有利な選択ができる。
- 社会的地位や経済的地位が高くなる傾向がある
地頭を鍛える8つの方法
①雑音を利用する
あえて雑音がある環境で作業や勉強をすることで脳に負荷がかかり前頭前野は鍛えられる
- 集中力が上がる
- ノイズを無視し、目の前のことに注意を向け続ける力向上
②タイムプレッシャー
制限時間を設けることで作業効率がアップし脳を鍛えることができる
- あらかじめ時間を決める
- 時間内に作業を終わらせるようにチャレンジ
- できるギリギリの時間に設定しゲーム性を設ける
- 設定の時間を短くしていき能力を高める
③マインドフルネス
気づき→自分の状態についてしっかりと気づけていること
- 集中力記憶力が上がる
- メンタル安定 ポジティブになる
- 共感力・コミュニケーション能力が上がる
- ダイエット効果
マインドフルネスの感覚を持てると過去や未来に囚われず「今この瞬間を生きれるようになる」
マインドフルネスのやり方
オーソドックスな方法は瞑想
- 1日3分だけを毎日続ける
- マルチタスクをやめる(テレビを見ながら食事をするなど)
- 日記(過去の自分と今の自分を比べ成長を実感)
④色々な体験をする
- スポーツ
- 旅
- 美術
- 映画
- 飲み会
- 読書
- 散歩
など日々の全てのインプットが脳に刺激を与え成長させる
脳がになっている役割
- 思考
- 感情
- 伝達
- 理解
- 運動
- 視覚
- 聴覚
- 記憶
これらの機能をまんべんなく使うことで脳全体が活性化しパフォーマンスが上がる
⑤脳に良い栄養をとる
- DHA⇒イワシやサバなどの青魚、アボカドなど
- チロシン(必須アミノ酸)⇒アーモンド・アボカド・バナナ・牛肉・鶏肉・チョコ・コーヒー・卵・緑茶・ヨーグルトなど
- トリプトファン(必須アミノ酸)⇒豚肉・牛肉・豆腐・納豆・味噌・ごま・乳製品など
- ポリフェノール⇒チョコ・大豆・緑茶・紅茶・コーヒー・赤ワイン・そば・たまねぎ・柑橘類など
- ビタミンB6⇒米・じゃがいも・牛肉・鶏肉・卵・乳製品・魚介類・野菜・ナッツ類など
⑥心理的安全状態を作る
- 危険
- 恐怖
- 不安
- 曖昧
- 未知
が少ない状態
⑦ノーシーボ効果を排除
=悪い思い込みを排除すること⇒悪い思い込みは脳のパフォーマンスを下げる
- どうせ俺には無理だ…
- やったって意味ない…
このような思い込みがあると能力が下がる=ノーシーボ効果(ネガティブな思い込みが能力を下げる)
根拠のない自信で良いから持とう。最初は根拠のない自信でも努力によって実績を作り、根拠のあるものにしていけば良い。
適度に自信をもち、最悪の状況を想定した上て色々なことにチャレンジしていく
⑧アハ!体験
なるほど、わかったなど分からなかったことが分かったり腑に落ちる時、どう言う意味だっけなー?と思い出そうとして思い出した!と思い出した時の体験。
このような体験をしたときにクリエイティブに関わる脳の回路が強化される。
AI時代に必要な能力
- コミュニケーション能力
- 想像力
- 直感力(センス)
人間らしさこそがAIに勝てる部分(発明・コミュニケーション・直感・センス・発想・アイデア・身体性
子供の地頭を良くするため生活に取り入られること
上記8項目を参考に子供達の地頭を良くするために取り入れられそうなことを考えてみました。
- リビングで学習する
- タイマーを使い時間を決めて勉強したり、ゲームをしたりする
- 食事の時はテレビをつけない ピアノの練習 寝る前に呼吸瞑想をする 1行日記
- 旅行、読書、スポーツ、映画、散歩、ボードゲームなど家族で楽しむ
- できるだけバランスの良い食事を心がける
- 生活リズムを整え、健康に過ごせるようにアシストする 親子で答えのない色々な話をする
- 子供の良い面を褒め、他人と比べず、子供自身のの過去と比べて成長を感じ伝える
- どんぐりくらぶの問題を活用し自分で考えることでアハ体験を積む
①リビングで学習する
多くの東大生が取り入れていたリビング学習は本当に有効なのか?スタサプのホームページにリビング学習の賛成意見、反対意見が記載されています。
賛成派の意見
・勉強中の姿を見守れるので安心できる
・子どもがいい意味でプレッシャーを感じる
・子どもの得手・不得手をチェックできる
・子どもの質問にその場で答えられる
・家族が子どもに注意してあげられる
・子どもが誘惑から逃げ出せる
・子どもが集中力を鍛えられる
反対派の意見
・リビングが汚れてしまう
・家族共有スペースが散らかってしまう
・集中できず効率が悪くなる
スタサプHPより
賛否両論あるようですが簡単に取り入れられそうなので、やってみる価値はあるのではないでしょうか?
我が家は地頭が良くなるとか全く考えていませんでしたが、子供達が小さい頃からリビング学習を取り入れています。1度やってみて合わない場合は無理に続ける必要はなく、合う場合はそれだけで地頭が良くなったらラッキーですよね。実際にリビング学習を取り入れているので反対派の意見もよくわかります。散らかるし、集中してない時も多々あり。それでも子供達が自分の部屋で勉強したいと言うまではこのままリビング学習スタイルでいきたいと思います。
- 散らかるのは教材や文房具を簡単に片付けられる場所を決めてしまえばよい
- 汚れは子供に自分で片付けてもらうことで片付ける力をつける
- 集中できない時は一旦違うことをして切り替える、そういう調節を自分で体験していくことで自分でコントロール出来るようになるのでは?
と考えています。
中学生の息子が定期テストの勉強を自分の部屋でしていた時がありました。その時のテストの点数が見事に低下したことを子ども自身が体験し、それ以来やっぱり誰かがいないとサボってしまうわーと言って自分でリビング学習を選択しています。他の家族はそれぞれ静かに自分の好きなことをして過ごしている感じで我が家はやっています。
②タイマーを使い時間を決めて勉強したり、ゲームをしたりする
きちんと時間を決めて問題を解くように日々していれば、テストの時も時間配分の管理が自然と出来るようになりそうですよね。
スマホのタイマーはついスマホを触ってしまいそうだし、100均一のタイマーは計ってる途中に切れていたりしたことがあるのでやめておいた方がよいです。オシャレなタイマーを選ぶことでモチベーションも上がりそうですね。
子供達に何時までに終わらせるか目標を決めて始めるように言っていますが、中々時間守れずダラダラ勉強をしていたり、ゲームをしてしまっています 。タイマーを使用し実行してみようと思います。
③食事の時はテレビをつけない ピアノなど楽器の練習 寝る前に呼吸瞑想をする 1行日記
食事中にテレビをつけない
食事中のテレビ
というワードで検索してみると色々な記事が出てきます。
https://gendai.media/articles/-/66589?page=1&imp=0
上の子が小学校の時「ご飯の時にテレビを見ている人」と先生が質問した時にほとんどの人が手を挙げて、自分と数人しかテレビを見ていない人がいなかったと子供が驚いて話してきたことがありました。我が家は食事の時にテレビをつけないスタイルで子供が小さい時からずっとやっています。子供にとってご飯中はテレビをつけないのが当たり前だと思っていたようで、みんなはテレビ見ながら食べるのかと驚いたのだそうです。地頭がどうとか全く考えていたわけではなく、ご飯をダラダラ食べられるのが嫌だっただけなのですがこの習慣が地頭を育てることにつながっているならラッキーです(笑)
子供が大きくなってきた我が家はたまにテレビをつけている日もありますし、テレビはつけずに会話をしながら食事をすることが多いです。
ピアノなど楽器の練習
私のように動画やラジオを聞きながら家事をするマルチタスクは地頭を鍛えるのには良くないようです(笑)
メンタリストDaiGoさんの本で楽器を習うと良いと読んだことがあります。
ピアノの練習は1つのことに集中する能力に繋がるのではと考えました。
我が家の子供達はピアノを習っています。ピアノを練習する時には先生に言われた事を思い出して意識して練習するようにとだけ子供達に言っています。それだけで毎日少ししか練習をしていませんが、日々成長を感じます。

寝る前に呼吸瞑想をする
3分間布団に入った時に瞑想する習慣をつけるようにしてみようと思います。これなら親子ともそんなに大変じゃないかなと。
1行日記
これね、ずっと取り入れたいなと思っていてまだ実行できていません。私は英語力をつける観点で取り入れたいと考えていたところでした。1行だけ毎日日記を書いて、それを英語に訳してオンライン英会話で通じるか話してみるという方法を独学英語を調べている時に見てこれなら取り入れられそうだと思っていたのです。日記が地頭を鍛えられるならすごく良いなと。子供達に良さを説明して乗り気じゃなかったら取り入れないかもしれませんが。嫌々やっても逆効果だし、結局やるのは子供なので。子供達の様子を見て提案してみようと思っています。

④旅行、読書、スポーツ、映画、散歩、ボードゲームなど家族で楽しむ
楽しんで地頭が鍛えられるなんて最高!色々な体験で脳にたくさん刺激を与え貴重な子供達との時間を楽しみたいです。
この本で今まで一番の思い出はと聞いて思い出すことは大抵が経験に基づいたこと。というように書かれていました。自分が子供の頃を思い出してもそうだなぁと感じるし、子供たちと話している時も、旅行の時の話とかよく覚えていて何度も会話に出てくるなと感じています。なので経験をして子供達が楽しかったなと思えることをたくさん作りたいですね。テーブルゲームとかも楽しくて良さそうです。

⑤できるだけバランスの良い食事を心がける
お菓子はダメとか、これを食べないととかそんな厳しいスタンスじゃなく、お菓子も食べるけど、普段色々な種類の食材を使って料理する、料理しなくても選ぶ時にバランスを気にかけて選ぶように意識することで意識しないよりは良くなりそうだなと考えてました。食事は毎日3回もあるので少しの意識の積み重ねで、健康にも関わってくるかなと考えています。
最近この本を読みました。食事だったら私にも出来るかもと思ったのです。私が普段意識していることと同じような印象を受けました。Kindle Unlimitedで無料で読めました。

⑥生活リズムを整え、健康に過ごせるようにアシストする 親子で答えのない色々な話をする
生活リズム
睡眠不足は体調不良につながるし、眠いとパフォーマンスがあがりませんよね。
10時までには寝て6時に起きる。やり残したことがある時は朝早く起きてやるように子供達に伝えています。
親子で答えのない話をする
もし~だったらどうする?と言う話をよくご飯中にしています。最近はNHKの番組を参考にしたり

お金の大学の動画を参考に
自分ならどうする?という話をたまにしています。こういう話ってAIには出来ないことですよね?
⑦子供の良い面を褒め、他人と比べず、子供自身の過去と比べて成長を感じ伝える
他人と比べないって中々難しいです。やはり競争社会で生きているので他人と比べて安心したり、落ち込んだり誰でも少なからずしてしまうものだと思います。他人と比べて頑張れるなら比べることで頑張る力にすれば良いし、メリットもたくさんあります。でも比べるのしんどいなと感じたり、自分の子が他人の子より出来ていないことが気になってモヤモヤしたりする時、兄弟で比べてしまうときは比べることをやめたら親子とも楽になれます。他人と比べられて色々言われたら「どうせ自分なんか・・・」とやっぱりなってしまうと思います。比べられて色々言われたら自分だったらいい気はしないです。比べてしまう事に疲れたら子供の過去に目を向けたら成長を感じられるし、まぁいっかと思えます。前は出来てなかったけど、出来るようになったね!と伝えた時子供はすごく嬉しそうな照れくさそうな顔をするんです。余裕のある時に1回やってみて下さい。
子供達がどうせ・・・と言い出した時これは良くないと思い調べたことがあり、出来て当たり前だと思っている小さな事でも伝えてみるようにしたんです。そしたら最近は、俺はできる人だからと自画自賛したり(息子)、自分でピアノを弾いて拍手したり(娘)してやたら自信を持っていて笑えます。いやいや、それレベル低いよと思ったとしても、子供達が自分で満足しているならそれでいっかと考えるようにしたら私自身が無意識のうちに他人と比べてしまうことは大分減りました。
⑧どんぐりくらぶの問題を活用し自分で考えることでアハ体験を積む
どんぐり倶楽部という学習方法があり、我が家は少し取り入れています。家で出来るのでお金はかからないです。

これね絵で解く算数の問題なのですが、親が教えないってゆうルールなんです。自分で考えて、あっ分かったっていうアハ体験が出来ると思います。
教えられた事はその時理解しても直ぐに忘れてしまうけれど、自分で考えて出来るようになったことって忘れにくくないですか?私は何となくそれを感じていて、子供達に勉強の事を聞かれたら教えられる事は一緒に考えて教えるけれど、必ずもう一度自分で出来るか確かめてと伝えています。出来ないことも同じ問題を自分で出来るまで何度もやれば必ず出来るようになるという経験をピアノでもしているし、勉強でも、運動でも何でも同じだよと話しています。
興味を持った方はどんぐり倶楽部調べてみてください。知る人ぞ知る学習法で、実際わたしのまわりの友達で知っていてやっている人はいないです。
まとめ
たくさんの情報がある中、みんなが良いという事でも、自分や家族にとっては合わないかもしれません。自分が取り入れてみたいなと思ったり、出来そうな事をやってみて、これは何か違うなと思ったらやめて、また出来そうな事を探してやってみて、の繰り返しが経験に繋がるし地頭の成長になるなら面白いなと思って記録しました。地頭をよくするために!と必死になりすぎて合わない事を無理に続けても楽しくないし、満足度は低い気がします。親子で楽しみ無理せず地頭の成長に結びついたらラッキーという感じで日々過ごせたらよいですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。何か少しでも参考になれば嬉しいです。
我が家は漫画を長期休暇のタイミングで購入するようにしています。子供たちは暇な時に読んでいます

テレビでやっていたのでへーと思い記録しました

子供たちが遊んでいたポケモンカードとかドラゴンボールカード、もう使わないので売って手放しました

小学校入学前に我が家が取り入れていたことの記録です